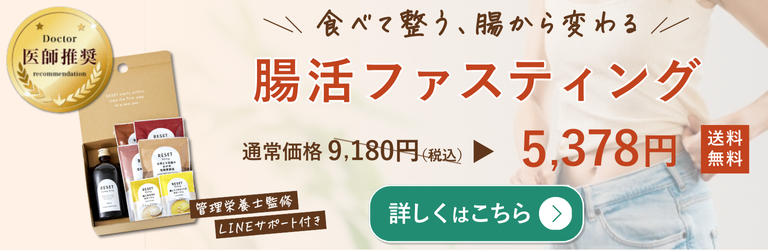RESET-Mediaへお越しいただきありがとうございます!皆様の参考となれば幸いです!
弊社商品の「RESET BOX」が2024年 からだにいいこと大賞にて、大賞をいただくことができました!RESET BOXは、これだけで3日間のファスティングが出来るファスティングキットです。
誰でも・簡単にファスティングができますので、「ファスティングに興味があるけどできそうにない」、「ファスティングをやる一歩が踏み出せない」といった方にお勧めですので、ぜひ確認してみてください!
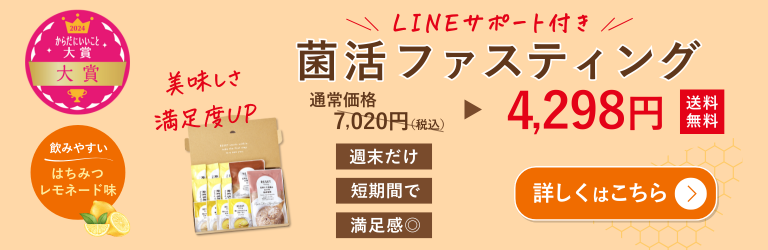
RESET BOXとFASTING BOXの違いはこちらの記事で解説しています。
関連記事:ファスティングセット比較|RESET BOXとFASTING BOXどっちがおすすめ?
玉ねぎの干し方を正しく行うことで、1年間の長期保存が可能になります。
家庭菜園で収穫した玉ねぎを無駄にしないために、この記事では収穫から天日干し、吊るし方、保存方法まで初心者にもわかりやすく解説します。
玉ねぎの正しい収穫時期と見極め方
 収穫のタイミングを見分けるポイント
収穫のタイミングを見分けるポイント
玉ねぎの収穫は5〜6月頃が一般的で、葉茎の変化を観察することで適切な収穫時期を見極めることができます。
最も重要なサインは、全体の80%程度の葉茎が倒れ始めることです。この状態になったら、さらに約1週間待ってから収穫を行います。また、とう立ちしている株が見られる場合や、首の部分が締まって硬くなってきた場合も収穫のタイミングといえるでしょう。
収穫が遅れると玉ねぎが腐りやすくなるため、これらのサインを見逃さずに適切なタイミングで収穫することが重要です。
品種別の収穫時期
| 品種 | 主な種類 | 収穫時期 | 保存期間 |
| 早生種 | 新玉ねぎ | 3〜5月 | 2〜3ヶ月 |
| 中生種 | ターポ | 5〜6月 | 6〜8ヶ月 |
| 晩成種 | ケルたま、 ネオアース |
5〜6月 | 10〜12ヶ月 |
玉ねぎの天日干し方法【基本手順】
収穫直後の処理
収穫した玉ねぎは、まず球についた土を手で軽く落としてから処理を始めます。
次に根の部分をハサミで切り落とし、葉は芽が出にくくなるよう20cmほど残してカットします。
この処理により栄養の分散を防ぐことができます。
天日干しの具体的手順
天日干しを成功させるためには、まず収穫後数日間晴天が続く日を選ぶことが重要です。風通しの良い場所で玉ねぎ同士が重ならないよう地面に並べ、1〜2日間直射日光に当てて表面を乾燥させます。乾燥の途中で裏返すことで、均等に乾燥させることができます。
天日干しを行う際は、長時間の直射日光が傷みの原因となるため避け、雨に濡れないよう天候に注意が必要です。また夜間は露に濡れないよう屋内に取り込むことをおすすめします。
玉ねぎの吊るし方と長期保存のコツ

吊るし保存に適した玉ねぎの準備
天日干し後の玉ねぎは吊るし保存の準備として、葉を15〜20cm残してカットし、傷んだ外皮を取り除いてから数個ずつまとめて紐で結びます。この処理により長期保存に適した状態に整えることができます。
おすすめの吊るし方法とネット
吊るし保存には様々な材料を活用できます。ストッキングを使用する場合は1本に5個程度入れて吊るし、みかんネットは形状が玉ねぎと似ており再利用に最適です。また市販の野菜保存用専用ネットも効果的です。
吊るし方の手順としては、まずネットに玉ねぎを1個入れてすぐ上を結び、玉ねぎ同士が接触しないようにします。次の玉ねぎを入れて同様に結ぶことを3〜5個程度まで繰り返し、最後に風通しの良い日陰に吊るします。
最適な保存場所の条件
玉ねぎの長期保存を成功させるためには、風通しが良く、日光が直接当たらない日陰で、雨が当たらない軒下やベランダなどの湿度が低い場所を選ぶことが重要です。これらの条件を満たすことで、玉ねぎを最適な状態で保存できます。
新玉ねぎの保存方法と注意点
新玉ねぎの特徴と保存の違い
新玉ねぎは水分含有量が多いため、通常の玉ねぎより保存期間が短くなります。
新玉ねぎの保存では、葉を切らずに残して紐で結んで吊るしたり、ネットに入れて吊るし保存することが効果的です。ただし、こまめな状態チェックが必要で、腐り始めたものは早めに取り除くことが重要です。
腐りやすい玉ねぎの見分け方
玉ねぎの腐敗は、頭部分を押すと水分が出る、表面が茶色に変色する、異臭がする、全体が柔らかくなるといった変化で見分けることができます。これらのサインを早期に発見することで、他の玉ねぎへの腐敗の広がりを防ぐことができます。
保存期間と品質管理のポイント

品種別保存期間の目安
正しい干し方と保存方法により、以下の期間保存が可能です。
-
晩生種:10〜12ヶ月(適切な環境下で翌年まで)
-
中生種:6〜8ヶ月
-
早生種・新玉ねぎ:2〜3ヶ月
長期保存成功のコツ
長期保存を成功させるためには、月1回程度の定期的な状態確認を行い、腐り始めた玉ねぎの早期発見・除去と吊るし紐の点検を怠らないことが大切です。
また、梅雨時期の湿度対策、冬季の凍結防止、通気性の確保といった環境管理も重要なポイントとなります。
よくある失敗例と対策
干し方の失敗パターン
玉ねぎの干し方でよくある失敗として、葉を切りすぎることが挙げられます。
葉を短く切りすぎると切り口から菌が侵入しやすくなるため、20cm程度は必ず残すことが重要です。また、天日干し不足も失敗の原因となり、表面が十分に乾燥していないと腐りやすくなります。最低1〜2日間はしっかりと乾燥させる必要があります。
さらに、湿度の高い場所での保存はカビや腐敗の原因となるため、風通しの良い乾燥した場所を選ぶことが大切です。
トラブル時の対処法
一部が腐り始めた場合は、腐敗部分を完全に取り除けば変色していない部分は使用可能です。
ただし、他の玉ねぎへの感染を防ぐため早めに処理することが重要です。また、吊るし紐が切れた場合は新しい紐で結び直し、ネットの場合は補強または交換を行います。
まとめ:玉ねぎの干し方成功のポイント

玉ねぎの干し方と長期保存を成功させるためには、適切な収穫時期の見極め(葉茎が倒れてから1週間後)、正しい天日干し(1〜2日間の十分な乾燥)、最適な保存環境(風通しが良く湿度の低い日陰)という3つのポイントが重要です。
これらのポイントを守ることで、家庭菜園で収穫した玉ねぎを1年間美味しく保存することができます。特に晩生種を選べば、翌年の収穫まで保存可能で、食費の節約にも大きく貢献します。
定期的な状態チェックを忘れずに行い、腐り始めた玉ねぎは早めに取り除くことで、他の玉ねぎも長期間美味しく保存できるでしょう。
なお、保存した玉ねぎは栄養価が高く、体内の代謝機能をサポートする硫黄化合物が豊富に含まれています。これらの成分は消化器官の働きを活性化し、内臓機能の向上に寄与するため、ファスティング(断食)前後の食事にも適しています。適切に保存された玉ねぎを活用することで、健康的なライフスタイルをより長期間維持することが可能になります。