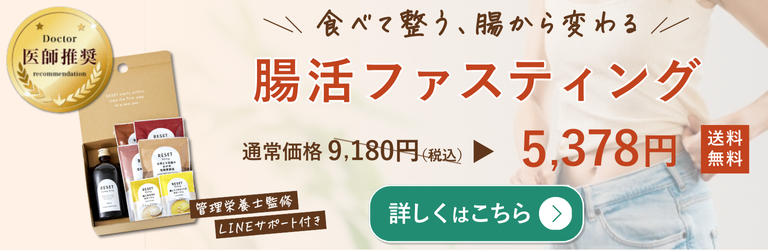RESET-Mediaへお越しいただきありがとうございます!皆様の参考となれば幸いです!
弊社商品の「RESET BOX」が2024年 からだにいいこと大賞にて、大賞をいただくことができました!RESET BOXは、これだけで3日間のファスティングが出来るファスティングキットです。
誰でも・簡単にファスティングができますので、「ファスティングに興味があるけどできそうにない」、「ファスティングをやる一歩が踏み出せない」といった方にお勧めですので、ぜひ確認してみてください!
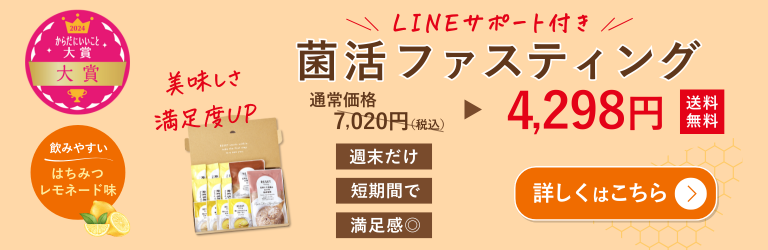
「腸活にいい食べものって、結局なにを食べればいいの?」
腸は“身体の健康の土台”といわれるほど大切な臓器です。食事を通して腸内環境を整えることで、便通や肌の調子、さらには心の安定にもつながります。
この記事では、腸活におすすめの食べものと避けたい食材、そして日常で無理なく続ける食習慣のコツを、管理栄養士の知見をもとにわかりやすく解説します。
今日から取り入れられるヒントを見つけて、あなたの“腸がよろこぶ食卓”を整えていきましょう。
腸活の始め方について悩んでいる方は、こちらの記事をご覧ください。
関連記事:腸活、何から始める?今日からできる腸内環境改善の3ステップ
関連記事:腸活の始め方|失敗しない順番と続けるコツをわかりやすく解説
腸活にいい食べ物とは?

腸活を続けるうえで欠かせないのが「毎日の食事」です。どんなにサプリを取り入れても、日々の食べ物が整っていなければ腸は本来の力を発揮できません。
腸にとっていい食べ物とは、腸内の善玉菌を増やしたり、腸の動きをサポートしたりする食材のこと。
なかでも「発酵食品」「食物繊維」「オリゴ糖」をバランスよく摂ることがポイントです。それぞれの役割を、もう少し詳しく見ていきましょう。
腸内環境を整える栄養素
「腸内環境を整える」とは、腸の中で善玉菌・悪玉菌などの菌たちがバランスよく共存できる状態にすることです。
腸の中には、善玉菌・悪玉菌・日和見菌と呼ばれる菌が住んでおり、このバランスが崩れると、便秘や肌荒れ、免疫力の低下などの原因になることもあります。
腸内の菌バランスを整えるために欠かせないのが、食物繊維・発酵食品・オリゴ糖の3つ。どれも身近な食材から手軽にとれる、腸活の基本栄養素です。
|
栄養素 |
はたらき |
食材例 |
|
食物繊維 |
便のかさを増やして腸の動きをサポート。 |
ごぼう、海藻、きのこ、豆類、野菜など |
|
発酵食品 |
善玉菌そのものをとり入れ、腸内のバランスを整える。 |
ヨーグルト、納豆、キムチ、味噌など |
|
オリゴ糖 |
善玉菌のエサとなり、腸内で短鎖脂肪酸をつくる。 |
玉ねぎ、バナナ、はちみつ、豆乳など |
3つを組み合わせることで、腸の調子が整います。
プロバイオティクス/プレバイオティクス/シンバイオティクスの違い
腸活でよく聞くこの3つの言葉。それぞれの意味を理解しておくと、食べ方のコツが見えてきます。
-
プロバイオティクス:腸に“良い菌”そのものをとり入れる
→ 例:ヨーグルト、納豆、ぬか漬け、キムチなど -
プレバイオティクス:腸内の善玉菌を“育てるエサ”をとり入れる
→ 例:オリゴ糖、食物繊維など -
シンバイオティクス:上の2つを“セットでとる”こと
→ 例:ヨーグルト+バナナ、納豆+海藻など
つまり、「入れて・育てる」両方を意識すると、腸の環境がより安定します。食べ合わせの工夫で、腸活効果を高めていきましょう。
発酵調味料の効果
発酵食品というとヨーグルトや納豆を思い浮かべがちですが、発酵調味料にも腸にうれしい働きがあります。
-
味噌:乳酸菌や酵母が豊富で、腸内の善玉菌をサポート
-
塩こうじ:酵素が食材をやわらかくし、消化を助ける
-
甘酒:「飲む点滴」と呼ばれるほど栄養豊富で、腸のエネルギー源になる糖分やオリゴ糖を含む
どれも加熱しすぎると菌が死んでしまうため、料理の仕上げに加えるのがベスト。
味噌汁を沸騰させずに温める、塩こうじは下味に使うなど、調理の工夫で効果をしっかり取り入れられます。
食物繊維の種類と働き
食物繊維には「不溶性」と「水溶性」の2種類があります。どちらも腸に欠かせませんが、役割が少し異なります。
- 不溶性食物繊維:便の量を増やし、腸を刺激して排出を促す
→ ごぼう、豆類、野菜の皮、穀類など - 水溶性食物繊維:腸内でゲル状になり、善玉菌のエサになる
→ 海藻、果物、オートミール、納豆など
理想のバランスは、不溶性:水溶性=2:1。たとえば「野菜+果物+海藻」を組み合わせると、自然にバランスが整います。
摂取量とバランスの目安
厚生労働省によると、1日にとりたい食物繊維の目安は女性で18g以上、男性で21g以上。
とはいえ、実際には多くの人が目標量に届いていません。コツは「1食ごとに少しずつ意識する」ことです。
例
-
朝:ヨーグルト+バナナ(菌+エサの組み合わせ)
-
昼:ごぼう入り味噌汁+玄米
-
夜:納豆+海藻サラダ
食物繊維は1日を通して分けて摂るのが理想的。無理せず続けられるペースで、少しずつ“腸にやさしい食卓”を整えていきましょう。
腸活にいい食材一覧と特徴

腸活にぴったりの食べ物は、日常の食卓にもたくさんあります。
「特別なものを用意しないと…」と思う必要はありません。いつもの食材を少し意識して選ぶだけで、腸にうれしい習慣がつくれます。
ここでは、代表的な“腸にいい食材”をタイプ別に紹介します。自分の好みやライフスタイルに合うものを見つけて、無理なく取り入れていきましょう。
発酵食品系
発酵食品は、腸に善玉菌そのものを届ける大切な存在です。
菌が生きたまま腸に届くことで、腸内フローラのバランスを整え、便通改善や免疫サポートにもつながります。
-
納豆:納豆菌が腸内で善玉菌の働きを助ける。ビタミンKやたんぱく質も豊富。
-
ヨーグルト:乳酸菌・ビフィズス菌を直接とり入れられる定番食材。好みの菌種で選ぶのが◎。
-
キムチ:植物性乳酸菌が豊富で、野菜の食物繊維も同時に摂れる。
-
ぬか漬け・チーズ:発酵によってうま味と栄養価がアップ。
発酵食品は加熱すると菌が減ってしまうため、なるべくそのまま食べるのがおすすめです。
食物繊維系
腸を動かし、老廃物をスムーズに排出するために欠かせないのが食物繊維です。
腸内の善玉菌のエサにもなり、腸内環境を底から整えます。
-
ごぼう・れんこん:不溶性食物繊維が豊富で、腸のぜん動をサポート。
-
海藻類(わかめ・昆布・もずく):水溶性食物繊維を含み、便をやわらかく整える。
-
きのこ類:低カロリーで食物繊維が多く、ダイエット中にも◎。
-
豆類(大豆・あずき・おからなど):腸内で善玉菌のエサとなるオリゴ糖も含む。
和食中心の食生活にするだけで、自然と腸が喜ぶメニューになります。
オリゴ糖系
オリゴ糖は、腸内の善玉菌の“エサ”になる成分です。とくにビフィズス菌を増やすはたらきがあり、腸の中をすこやかに保ってくれます。
-
玉ねぎ・ねぎ・にんにく:加熱してもオリゴ糖が残りやすいので、スープや炒め物にも◎。
-
バナナ:朝食や間食に取り入れやすい腸活フルーツ。発酵食品との相性も抜群。
-
はちみつ:天然のオリゴ糖が豊富。ヨーグルトにかけて“シンバイオティクス食”に。
甘みをプラスしたいときに砂糖の代わりに使うのもおすすめです。
ポリフェノール系
ポリフェノールは抗酸化作用をもち、腸内で悪玉菌の増殖をおさえるはたらきがあります。
また、腸の炎症を防ぎ、善玉菌がすみやすい環境づくりにも役立ちます。
-
緑茶・紅茶:カテキンが悪玉菌を抑え、腸内をすっきり整える。
-
カカオ(高カカオチョコレートなど):腸内のビフィズス菌を増やす研究も報告あり。
-
ブルーベリー・ぶどう:アントシアニンが抗酸化に優れ、美容にも◎。
甘いお菓子を食べる代わりに、カカオ70%以上のチョコを選ぶのも腸活のひと工夫です。
腸内環境を助ける油脂・脂質系
油は“悪者”と思われがちですが、良質な脂質は腸にも大切です。とくにオメガ3系の油は、腸の炎症をおさえる効果が期待できます。
-
オリーブオイル:ポリフェノールを含み、腸の潤滑油のような働き。
-
アマニ油・えごま油:オメガ3脂肪酸が豊富で、腸内の炎症ケアに。
-
ナッツ類(アーモンド・くるみなど):食物繊維+良質脂質のダブル効果。
サラダにかける、スープにひとたらしなど、“生”で摂るのが効果的です。
発酵調味料
調味料の形で毎日の食事にとり入れられるのが、発酵調味料の魅力。発酵によって生まれる酵素やアミノ酸が、腸内の善玉菌をサポートします。
-
味噌:乳酸菌や麹菌が豊富。味噌汁は“腸活スープ”としても優秀。
-
塩こうじ:料理の下味に使うだけで、消化しやすくうま味もアップ。
-
甘酒:オリゴ糖やビタミンB群を含み、腸のエネルギー補給にも。
毎日の料理に自然に取り入れられるので、無理なく続けたい腸活アイテムです。
甘酒についてもっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
関連記事:甘酒は太るって本当?ダイエットにいい飲み方について管理栄養士が解説
腸活に合う飲み物
腸を整えるには、何を飲むかも大切。水分は腸内の老廃物を流す“掃除役”のような存在です。
-
常温水:冷たい水より腸にやさしく、朝一杯の白湯は腸の目覚ましにも。
-
お茶(緑茶・麦茶・ルイボスティーなど):カフェインレスのものなら夜でも◎。
-
酵素ドリンク:発酵の力で腸内の消化吸収をサポート。ファスティング中にもおすすめ。
酵素ドリンクの選び方は、こちらをご覧ください。
関連記事:酵素ドリンクの選び方|味・成分・サポートで続けやすい商品を選ぶコツ
腸活中に避けたい食べ物

どんなに良い食材をとっていても、腸に負担をかける食べ物を続けてしまうと、腸内環境は乱れやすくなります。
「食べない」よりも、「控える」意識でOKです。腸が整う食事とそうでない食事の違いを知っておくだけでも、毎日の選択が変わります。
ここでは、腸活中に気をつけたい代表的な食べ物を紹介します。
高脂肪・高糖質な食品
揚げ物やスナック菓子、ファストフードなどの脂っこい食事は、腸のぜん動を鈍らせ、悪玉菌を増やす原因になります。
また、ケーキや菓子パンなどに多い砂糖の摂りすぎも注意。糖質は悪玉菌のエサとなり、腸内バランスを崩してしまいます。
とはいえ、ストレスにならない範囲で楽しむことも大切です。「毎日は避ける」「量を半分にする」など、無理のないペースでコントロールしていきましょう。
添加物・人工甘味料の影響
加工食品や清涼飲料水に含まれる保存料・着色料・人工甘味料は、腸内の善玉菌に影響を与えることがあります。
とくに人工甘味料(アスパルテーム・スクラロースなど)は、血糖値には影響しにくい一方で、腸内細菌の構成を変えるという報告もあります。
コンビニ食を選ぶときは、原材料表示をチェックしてみましょう。「保存料不使用」「シンプルな原材料」で作られた商品を選ぶだけでも、腸へのやさしさが変わります。
小麦・乳製品などFODMAPに注意が必要な食材
腸内環境が乱れている人の中には、小麦や乳製品などのFODMAP(発酵性食物成分)に敏感なタイプもいます。
これらは腸内でガスを発生させやすく、お腹のハリや痛み、便秘や下痢を引き起こすことがあります。
-
小麦:パン・パスタ・うどんなど
-
乳製品:牛乳・生クリームなど
-
豆類・果糖の多い果物 も一部注意
一度にたくさん食べず、少量ずつ試す・発酵食品で補うなど、自分の体と相談しながら調整しましょう。
発酵食品でも食べ過ぎ・加熱による菌死滅リスク
腸活に良いとされる発酵食品も、「多ければ良い」というわけではありません。
食べすぎると塩分や糖分の摂りすぎになり、かえって腸に負担をかけることもあります。
また、ヨーグルトや味噌汁などを高温で加熱すると、せっかくの善玉菌が死滅してしまうことも。
味噌汁は火を止めてから味噌を溶く、ヨーグルトは冷たいまま食べるなど、“菌を生かす食べ方”を心がけましょう。
「良かれと思って食べていた」落とし穴
一見ヘルシーに見える食品でも、腸にとっては逆効果になることがあります。
例
-
野菜ジュース:砂糖や添加物が多いものは注意
-
グラノーラ:甘味料や油が多く、腸に負担がかかるタイプも
-
低糖質スイーツ:人工甘味料が多く含まれている場合も
「ヘルシー=腸にいい」とは限りません。パッケージのイメージだけで選ばず、原材料を見る習慣をつけておくと安心です。
腸活によい食べ方・タイミング

腸にいい食材を選ぶだけでなく、「いつ・どう食べるか」もとても大切です。
同じ食材でも、食べる時間や組み合わせを意識するだけで、腸への届き方や働き方が変わります。
腸がよろこぶ食べ方のコツを、時間帯別に見ていきましょう。
朝に摂るとよい発酵食品と食物繊維
腸は朝に活発に動き始めます。起きてすぐに白湯を飲むことで腸をやさしく目覚めさせ、そのあとに発酵食品+食物繊維をとると、腸内環境のスイッチがONに。
おすすめの組み合わせ
-
ヨーグルト+バナナ(善玉菌+オリゴ糖)
-
納豆+海藻(菌+食物繊維)
-
味噌汁+玄米(発酵+食物繊維)
朝食で「菌を入れて・育てる」流れを作ると、1日を通して腸が整いやすくなります。
夜は腸を休ませるメニューを選ぶ
夜は腸が休息モードに入る時間です。消化に時間がかかる脂っこい食事や、夜遅い時間の食事は腸に負担をかけてしまいます。
夜は次のようなポイントを意識しましょう。
-
消化の良い食材(おかゆ・スープ・豆腐など)を中心に
-
量は腹八分目
-
寝る3時間前までに食事を終える
腸がゆっくり休むことで、翌朝の排便リズムも整いやすくなります。
「夜は整える時間」と考えて、胃腸にやさしいごはんを意識しましょう。
食べる順番・組み合わせ・温度による違い
同じ食事でも、食べる順番や温度を少し変えるだけで腸への影響は大きく変わります。
-
野菜→たんぱく質→炭水化物の順で食べると、血糖値の急上昇を防ぎ、腸の負担を軽減。
-
温かいものを取り入れると、腸の血流がよくなり、動きがスムーズに。
-
発酵食品+食物繊維をセットにすると、善玉菌を“入れて育てる”相乗効果が生まれます。
ちょっとした意識で、同じメニューでも腸のコンディションがぐっと変わります。
加熱・冷やしの調理で変わる腸活効果
腸活食材は、調理方法でも働き方が変わるのが特徴です。
例
-
加熱した野菜はかさが減り、食物繊維を無理なく多く摂れる
-
冷ましたごはん(レジスタントスターチ)は、腸内で食物繊維のように働く
-
味噌や塩こうじなどの発酵調味料は、加熱しすぎず“仕上げに加える”ことで菌を生かせる
「火を通してやわらかく」「冷やして変化を楽しむ」など、調理の工夫で腸に届く栄養が変わることを覚えておくと◎です。
日常で無理なく続ける腸活食習慣

腸活は、短期間で変化を求めるものではなく、“続けることで育つ習慣”です。完璧を目指さず、「できることを、できる範囲で」続けることが一番の近道。
ここでは、忙しい毎日でも無理なく取り入れられる腸活の工夫を紹介します。
コンビニ・外食でも腸活チョイス
「自炊する時間がない…」という日でも、選び方次第で腸活は続けられます。たとえば、コンビニではこんな組み合わせがおすすめです。
-
おにぎり(玄米や雑穀入り)+味噌汁
-
納豆巻き+野菜スープ
-
サラダチキン+海藻サラダ+ヨーグルト
外食でも、和食・定食スタイルを選ぶと自然に腸が整いやすくなります。汁物・副菜・発酵食品を意識するだけで、腸活メニューに早変わりです。
食品ラベルの見方で添加物を避ける
腸活を意識するなら、「何を食べるか」だけでなく「何が入っているか」にも目を向けてみましょう。
食品ラベルを見る習慣をつけると、自然と体にやさしい選択ができるようになります。
ポイントは3つ。
-
原材料がシンプル(読める言葉で書かれている)
-
「保存料」「人工甘味料」「香料」などが少ない
-
砂糖や油脂が最初に書かれていない
最初は少し面倒でも、慣れてくると“腸がよろこぶ商品”を見つける目が養われていきます。
ストック食材とRESET BOXの活用
腸にやさしい以下の食材を常備しておくと、忙しい日も安心です。
-
常温保存できる味噌や塩こうじ
-
海藻・きのこ・豆類の乾物
-
オートミール・玄米パック
このような食材をストックしておくと、さっと整う一品がつくれます。
さらに、RESET BOXのようなファスティングサポート食を活用するのもおすすめです。
酵素ドリンクや発酵スープ、ミールがセットになっているため、「腸を整えたいけれど時間がない」方でも、簡単に腸活リセットができます。
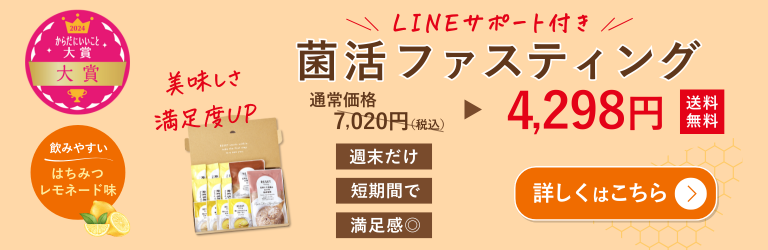
挫折しないための考え方
腸活を続けるうえで大切なのは、「できない日があっても大丈夫」と思えること。
ストレスや罪悪感は、実は腸にもよくありません。
-
甘いものを食べた日があっても翌日リセットすればOK
-
週末は少し休む“ゆる腸活”でも◎
-
“続けられるリズム”こそが一番の成果
腸はあなたのペースをちゃんと覚えており、心地よく続けることがいちばんの腸の栄養になります。
まとめ|“腸にいい食事”を日常にするリセット習慣
腸活にいい食べ物や飲み物は、特別なものではなく、いつもの食卓にたくさんあります。
発酵食品や食物繊維、オリゴ糖を中心に、バランスよく食べること。
そして、無理せず“続けられる形”で取り入れることが、腸活成功の秘訣です。
腸が整うと、体も心も軽やかに。朝の目覚めや肌の調子、気分までも変わっていきます。
毎日の食事を少し見直して、“腸がよろこぶリセット習慣”をはじめてみましょう。