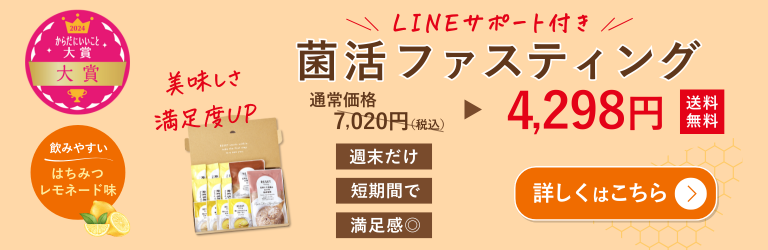酵素ドリンクを使ったファスティングはこちらの記事で詳しく説明しております。
関連記事:酵素ドリンクファスティングのやり方|RESET BOXで簡単に週末菌活断食
プロテインを飲んだあとに「お腹がゴロゴロする」「下痢になった」といった経験はありませんか?
筋トレやダイエット、美容のためにプロテインを取り入れている人は多いですが、実は飲み方や体質によってはお腹を壊すことがあります。
せっかく健康のために飲み始めたのに、体調を崩してしまっては本末転倒ですよね。この記事では、プロテインでお腹を壊す主な原因や、体質に合った選び方・対策方法を管理栄養士監修のもとでわかりやすく解説します。
自分に合った方法を見つけて、プロテインを快適に取り入れていきましょう!
プロテインでお腹を壊す主な5つの原因

プロテインを飲んだあとにお腹を壊してしまうのは、決して珍しいことではありません。
実はその原因には、体質や飲み方、プロテインの種類など、さまざまな要素が関係しています。
ここでは、お腹の不調につながりやすい代表的な原因を5つ解説します。
乳糖不耐症の可能性
プロテインのなかでも「ホエイプロテイン」は牛乳由来のため、乳糖(ラクトース)という成分が含まれています。
この乳糖を体内でうまく分解できない体質の人が「乳糖不耐症」です。
乳糖不耐症の人が乳糖を含むプロテインを摂取すると、腹痛や下痢、ガス溜まりなどの症状が出やすくなります。
普段牛乳やヨーグルトでお腹がゴロゴロする方や、ホエイプロテインを飲んで不調を感じる場合は、乳糖不耐症を疑いましょう。
人工甘味料・添加物の影響
多くのプロテイン製品には、味を良くするために人工甘味料や香料、保存料などが含まれています。
とくに「スクラロース」「アセスルファムK」などの甘味料は、一部の人にとって腸への刺激となり、下痢やお腹の張りを引き起こすことがあります。
無味のプレーンタイプや、甘味料を天然由来(ステビアなど)に置き換えた製品を選ぶことで、症状が改善するケースもあります。
たんぱく質の過剰摂取
たんぱく質は体に必要な栄養素ですが、一度に多く摂りすぎると消化に負担がかかり、下痢や胃もたれの原因になります。
プロテイン1杯あたりの摂取量は製品にもよりますが、20g前後です。
体重や運動量に応じて適量を見極めずに、1日何度もプロテインを飲んでいると、腸内環境を乱すおそれもあります。
空腹時・冷たい水での摂取で胃腸に負担がかかる
朝起きてすぐや、食事を抜いた後などに空腹状態で冷たいプロテインを一気に飲むと、胃腸への刺激が強くなりがちです。
とくに胃腸が敏感な方は、急激な温度差や濃度の高いたんぱく質により、腹痛や下痢を引き起こすことがあります。
ぬるめの水や割もので、ゆっくり飲みましょう。
腸内環境や体質との相性
プロテインが原因というよりも、もともとの腸内環境の乱れや体質によって、不調が起きやすいこともあります。
たとえば、便秘や下痢を繰り返している人やストレス、睡眠不足が続いている人は、腸のバリア機能が弱まっている可能性も。
腸内フローラのバランスが乱れている状態では、プロテインに限らずさまざまな食品で不調が出やすくなります。
プロテインでお腹を壊さないための5つ対策

お腹の不調を感じたからといって、すぐにプロテインをやめる必要はありません。
体質に合わせた工夫をすれば、快適に取り入れられるケースがほとんどです。
ここでは、プロテインでお腹を壊さないためにできる5つの対策を紹介します。
乳糖の少ないWPIやソイプロテインに切り替える
乳糖が原因と思われる場合は、「WPI(ホエイプロテインアイソレート)」や「ソイプロテイン」に切り替えるのが有効です。
WPIは乳糖がほぼ除去されており、ソイプロテインは大豆由来で植物性のため、胃腸への負担が少ないとされています。
人工甘味料・添加物が少ない製品を選ぶ
腸への刺激を抑えるためには、できるだけナチュラルな製品を選びましょう。
成分表示をチェックして、人工甘味料や添加物の少ない製品を選ぶことが大切です。
「無添加」「プレーン味」などの表記がある製品は、敏感な人にも比較的安心です。
分量を減らして様子を見る
不調を感じたら、まずは摂取量を少なめに調整してみましょう。
プロテイン1回分の標準は20g前後ですが、10gほどにして様子を見るのもおすすめです。
たんぱく質の量を減らすことで、消化吸収の負担を軽減できます。
ぬるめの水でゆっくり飲むようにする
冷たい水で一気に飲むのではなく、常温〜ぬるめの水で少しずつゆっくり飲むことで胃腸への負担を軽減できます。
とくに朝食代わりに飲む場合などは、この工夫だけでも不調が軽減されることがあります。
食後や間食タイミングに摂る
プロテインの摂取タイミングは、空腹時を避けましょう。
食後や間食としてプロテインを摂ることで、胃腸への刺激を抑えられます。
ほかの栄養と一緒に摂ることで吸収もスムーズになりやすいです。
お腹にやさしいプロテインの選び方

体質に合ったプロテインを選ぶことは、お腹の不調を防ぐうえでとても大切です。
ここでは、購入時にチェックしたいポイントを紹介します。
WPI(ホエイプロテインアイソレート)か、ソイプロテインがおすすめ
乳糖に弱い方には、乳糖を除去したWPIタイプや、植物性のソイプロテインがおすすめです。
| 種類 | 特徴 |
| WPI(ホエイプロテインアイソレート) | ・乳脂肪や乳糖が除去 ・吸収が早い |
| ソイプロテイン | ・大豆イソフラボン含有 ・吸収がゆっくり |
WPIとソイプロテインは、それぞれ特徴が異なるので目的に合わせて選びましょう。
商品の口コミやレビューを参考にする
実際の利用者の口コミやレビューは、自分に合ったプロテインを見つけるうえで、とても参考になります。
「これを飲んでお腹を壊した」「下痢になった」といったネガティブな口コミがある場合には注意が必要です。
ただし、プロテインとの相性は人それぞれ。
その人の体質や飲み方が影響していることもあるため、口コミはあくまで参考程度にとどめましょう。
それでも合わない場合の対処法・注意点

ここまでの対策を試してもなお不調が続く場合は、次のような選択肢も検討してみましょう。
腸内環境を整える
慢性的な下痢や便秘がある場合は、まず腸内環境を整えることが先決です。
発酵食品や食物繊維、睡眠・ストレスケアなど生活習慣の見直しも大切になります。
腸内環境を整えるには、次のような方法が効果的です。
-
発酵食品(ヨーグルト・納豆・キムチなど)を意識して摂る
-
水溶性食物繊維(海藻類・オートミール・野菜類)をしっかり補う
-
スマホやカフェインの摂りすぎを見直し、睡眠・ストレス管理を行う
-
暴飲暴食を避け、消化にやさしい食事を心がける
腸の土台が整うことで、プロテインだけでなく日々の食事の吸収効率も上がり、体調や美容にもよい変化が期待できます。
また、腸を一度リセットする方法として「ファスティング(プチ断食)」も注目されています。
ファスティングは、消化器官を一時的に休ませることで、腸内環境のリズムを整えることができ、便通の改善や肌荒れの軽減にもつながると言われています。
ただし、やみくもに自己流で行うと栄養不足やリバウンドのリスクもあるため、専門家のサポートつきでおこないましょう。
初心者でも簡単にファスティングができるRESET BOXについては、こちらの記事で解説しています。
関連記事:初心者向け酵素ドリンクファスティング|話題の菌活リセット法を解説
栄養は食事メインに戻すのもアリ
プロテインがどうしても体に合わないと感じたときは、無理に飲み続ける必要はありません。
まずは、通常の食事からたんぱく質をしっかり摂ることを優先しましょう。
たんぱく質は、次のような食材で無理なく補えます。
-
卵
-
豆腐・納豆・味噌汁などの大豆製品
-
鶏むね肉・ささみ
-
白身魚(タラ・鱈・カレイなど)
とくに胃腸が敏感な方は、焼く・揚げるよりも、蒸す・煮る・茹でるといった調理法がおすすめです。
冷えたお弁当よりも、温かい汁物や雑炊、茶碗蒸しなどのやさしいメニューの方が、体に負担をかけにくくなります。
体質に合うプロテインに出会うまで試行錯誤が必要な場合もある
プロテインとひとくちに言っても、ホエイ・ソイ・カゼイン・ピープロテインなど種類はさまざまで、体質との相性にも個人差があります。
「A社のホエイはお腹を壊したけど、B社のソイなら大丈夫だった」
「無添加タイプはOKだけど、甘味料入りは合わなかった」
というように、成分のちょっとした違いが不調の原因になっていることも少なくありません。
たとえば、こんなステップで試すのがおすすめです。
①今飲んでいるプロテインの成分をチェック
( 乳糖入り?人工甘味料は?添加物は多い?)
②「WPI(ホエイプロテインアイソレート)」や「ソイ」「ピープロテイン」に切り替える
( 乳糖・添加物の少ない製品を選ぶ)
③1日半量程度からスタートして、2〜3日様子を見る
( 症状が出るか、飲み方(時間帯・温度)も合わせて検証)
④不調が出た場合は成分ごとに原因を切り分ける
( 乳成分か、甘味料か、摂取量か など)
体調に合うものが見つかるまで、最低でも2〜3種類は試してみる価値があります。
「一回ダメだった=体質に合わない」と決めつけず、焦らず段階的に試す姿勢が大切です。
また、プロテインは飲み方・飲むタイミングによっても体への影響が変わります。
「朝食代わりに飲むとダメだけど、間食なら平気だった」というケースもあるため、一度NGだったものも、飲み方を変えて再トライすることで意外と合う場合もあります。
プロテインとの相性は個人差が大きいため、一度でうまくいかなくても落ち込む必要はありません。
焦らず、体と相談しながら少しずつ試していきましょう。
まとめ:プロテインと上手く付き合おう!
プロテインでお腹を壊す原因は人それぞれですが、多くの場合は体質や飲み方、成分の相性が関係しています。
今回ご紹介した原因や対策を参考に、自分に合ったプロテインを見つければ、無理なく快適に続けることができます。
「合わないからやめる」ではなく、「自分に合う方法を探す」という前向きな気持ちで、プロテインを取り入れていきましょう!