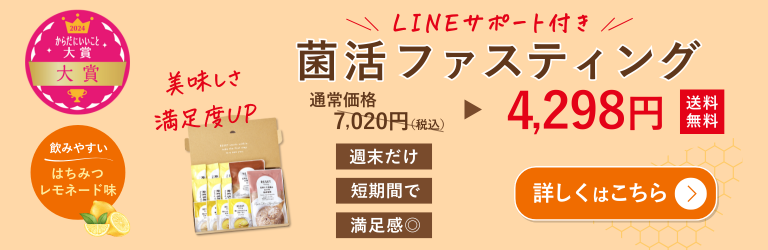RESET-Mediaへお越しいただきありがとうございます!皆様の参考となれば幸いです!
弊社商品の「RESET BOX」が2024年 からだにいいこと大賞にて、大賞をいただくことができました!RESET BOXは、これだけで3日間のファスティングが出来るファスティングキットです。
誰でも・簡単にファスティングができますので、「ファスティングに興味があるけどできそうにない」、「ファスティングをやる一歩が踏み出せない」といった方にお勧めですので、ぜひ確認してみてください!
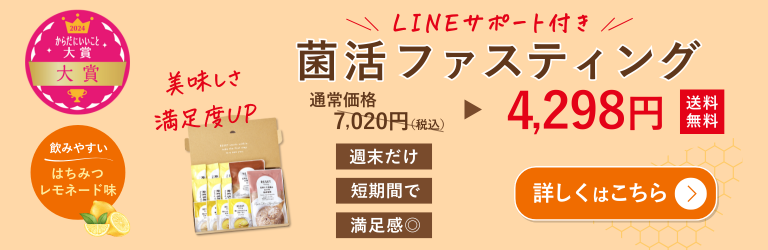
酵素ドリンクを使ったファスティングはこちらの記事で詳しく説明しております。
関連記事:酵素ドリンクファスティングのやり方|RESET BOXで簡単に週末菌活断食
ファスティングや健康診断の前に耳にする準備食。
「どんな食事をすればいいの?」「いつから始めるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
準備食は、胃腸を整えて身体をスムーズに切り替える大切なステップです。正しく取り入れることで、断食や検査を安全に進められるだけでなく、体調不良を防ぐ効果も期待できます。
この記事では、準備食の基本から目的、開始時期、食材選び、避けるべき食品、具体的なメニュー例まで徹底解説します。
これからファスティングや健康診断を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
準備食とは?

準備食は具体的にどんな食事を指すのか、どんな場面で取り入れるのかは意外と知られていません。
ここでは、準備食の基本的な考え方や、実際に活用されているシーンを詳しく見ていきましょう。
準備食とは身体を整える食事
準備食とは、身体を整えるために摂る消化に優しい食事です。普段の食生活で負担をかけている胃腸を休ませながら、必要な栄養を取り入れることを目的にしています。
とくにファスティングや医療処置の前は、急に絶食すると体調不良につながるため、準備段階で「食べる内容を整える」ことが大切です。
活用されるシーン
準備食は以下のような場面で取り入れられます。
| シーン | 目的・効果 |
| ファスティング前 | 断食に備えて胃腸をリセットし、スムーズに絶食へ移行できる |
| 健康診断・人間ドック前 | 脂質や糖質を控え、検査結果の精度を高める |
| 手術・治療前 | 麻酔や処置のために消化の良い食事をとり、体への負担を軽減する |
| ダイエット開始前 | 急激な制限による体調不良を防ぎ、無理なく食生活を切り替える |
つまり準備食は身体への負担を減らし、スムーズな切り替えをサポートする食事といえます。
準備食の目的と役割

準備食の大きな目的は、胃腸を休めて身体を整え、不調を防ぎながら次のステップにつなげることです。
適切におこなうことでファスティングや医療処置の成功率が高まります。
胃腸を休ませて消化をリセット
普段の食生活では、油分の多い料理や加工食品、添加物を含む食事によって、胃や腸に大きな負担がかかっています。
そこで準備食では、消化に優しい食材を中心に取り入れることで、疲れた胃腸を休ませ、本来の働きを整えられます。
身体をリセットする過程を経ることで、断食や健康診断当日へも無理なく移行しやすくなるのです。
糖質・脂質を控えて代謝を整える
揚げ物や甘いスイーツなどは、血糖値を乱しやすく、脂肪の蓄積にもつながります。準備食の段階で糖質や脂質を控えると、血糖値や中性脂肪が安定し、肝臓やすい臓への負担も軽くなります。
その結果、代謝のバランスが整い、ファスティング中には脂肪燃焼へとスムーズに切り替わりやすくなるのです。
頭痛・便秘などトラブルを予防
断食を始めた直後には、身体が急な変化に適応できず、頭痛や便秘、倦怠感といった不調が起こりやすくなります。しかし準備食を取り入れることで、カフェインや糖質・脂質の摂取を事前に減らし、身体を少しずつ慣らしていけるのです。
その結果、断食本番での体調不良を防ぎやすくなり、快適に続けられる可能性が高まります。
実際に「準備をした人の方がファスティング成功率が高い」と言われるのも、このためです。
水分・食物繊維で排出をサポート
野菜や海藻、きのこ、発酵食品といった食材には、腸内環境を整える働きがあります。これらを準備食に取り入れ、水分とあわせて十分に補給することで、便通がスムーズになり老廃物の排出が促されます。
デトックス効果を高められるため、ファスティング中も身体が軽く感じられ、より快適に過ごすことができるでしょう。
準備食はいつから始める?

準備食は「どのくらい断食するのか」「どんな目的で行うのか」によって開始時期が変わります。期間に応じて適切なタイミングを知ることで、体に無理なく取り入れることができます。
ファスティング期間に応じた開始目安
ファスティングの場合は、断食期間に応じて準備食を開始しましょう。
1日だけの断食であれば、前日から意識するだけでも十分です。揚げ物やお肉など消化に負担のかかる料理は控え、野菜中心の軽い食事に切り替えておくと、翌日の断食をスムーズに始められます。
3日間のファスティングを行う場合は、少なくとも2〜3日前から準備食を取り入れるのが理想的です。食事の内容を段階的に軽くし、糖質や脂質を少しずつ減らしていくことで、断食本番の身体への負担を最小限に抑えられます。
さらに1週間以上の長期断食を予定している場合は、1週間ほど前から準備食を始めると安心です。食べる量や内容を徐々に整えることで、身体がスムーズに絶食へ移行でき、断食中の不調も起こりにくくなります。
健康診断・手術など医療シーンでの準備期間
準備食は、ファスティングだけでなく健康診断や医療シーンでも欠かせません。
たとえば一般的な健康診断や人間ドックでは、前日の夜から脂っこい料理やアルコールを避け、消化にやさしいおかゆやうどん、野菜中心の食事を心がけると検査がスムーズに行えます。
また、大腸内視鏡検査や手術を予定している場合は、医師から指示された食事制限に従うことがとても重要です。多くの場合、2〜3日前から繊維の多い野菜や消化に時間がかかる食品を控えるよう求められます。
事前に準備食を意識することで、検査当日の体調を整えるだけでなく、麻酔や処置を安全に受けることにもつながります。
1日だけでも意味はある?
準備食は本来、数日間かけて行うのが理想ですが、忙しくて十分な期間を取れない場合でも、前日だけ取り入れることには意味があります。たとえ1日でも食事を軽くし、油っこい料理やアルコールを控えることで、胃腸の負担を減らせます。
その結果、断食や健康診断へスムーズに移行でき、体調不良を防ぐ効果も期待できます。
準備食を始めるタイミングについては、こちらの記事で詳しく解説してます。
関連記事:準備食はいつから?1日・3日・断食期間別の開始目安と注意点
準備食におすすめの食材
準備食を成功させるためには、「何を食べるか」を意識することが欠かせません。胃腸にやさしく、体調をスムーズに整えてくれる食材を選ぶことで、その後のファスティングや検査もぐっと快適になります。
ここでは、具体的にどんな食材が準備食に適しているのかを紹介します。
「まごわやさしい」の考え方(豆・ごま・わかめ・野菜・魚・しいたけ・いも)
準備食でよく取り入れられるのが、日本の伝統的な健康食のキーワードである「まごわやさしい」です。
| 頭文字 | 食材の例 |
| ま | 豆腐・納豆・枝豆 |
| ご | ごま・ナッツ類 |
| は | わかめ・昆布・ひじき |
| や | 根菜・葉物野菜・トマト |
| さ | 白身魚・青 |
| し | しいたけ・しめじ・えのき |
| い | さつまいも・じゃがいも・里芋 |
これらの食材は消化が良く、栄養バランスも整いやすいため、準備食にぴったりです。
「まごわやさしい」を意識すれば、準備食でも自然と栄養バランスが整い、身体を優しくリセットできます。
発酵食品(味噌・漬物・ヨーグルトなど)
腸内環境を整えるには、発酵食品をうまく取り入れることが効果的です。味噌汁に使う味噌や漬物、納豆、ヨーグルトなどは乳酸菌や酵母が含まれ、腸内の善玉菌をサポートしてくれます。
ただし塩分が高いものもあるため、量は控えめにしながら毎食少しずつ取り入れましょう。
穀類・おかゆ・うどん・スープ
主食は、白米よりも消化にやさしいおかゆや雑炊、うどんなどを選ぶと安心です。柔らかく煮込むことで胃腸への負担が減り、スムーズに吸収されます。
また、具だくさんの野菜スープや味噌汁は、水分と栄養を同時に補えるため、準備食の定番メニューといえるでしょう。
準備食でおすすめの食材については。こちらの記事で紹介しています。
関連記事:ファスティングの準備食で食べてはいけないものは?管理栄養士が解説
準備食で避けたいNG食品

準備食では「何を食べるか」と同じくらい「何を避けるか」も大切です。
普段の食事でよく口にしている食品の中には、胃腸に負担をかけたり、断食や検査に向けた体づくりを妨げてしまうものがあります。ここでは特に注意したい食品を整理しておきましょう。
肉・揚げ物など脂っこい料理
トンカツや唐揚げ、フライドポテト、ステーキや焼肉のようなこってりした料理は、準備食には不向きです。これらを食べたまま断食や検査に入ると、胃もたれや不快感を招くだけでなく、腸に食べ物が長く残ってしまい、せっかくの準備が台無しになることもあります。
準備食の期間は、肉類の中でも消化が比較的良い白身魚や豆腐などの植物性たんぱく質を選びましょう。
砂糖・スイーツ・ジャンクフード
ケーキやドーナツ、アイスクリーム、チョコレート、清涼飲料水などの砂糖を多く含む食品は、血糖値の乱高下を招き、頭痛やだるさにつながります。インスタントラーメンやスナック菓子、ファストフードのハンバーガーやポテトも添加物や油分が多く、腸内環境を乱しやすいため、準備食では控えるべきです。
代わりに、果物の自然な甘みや蒸しさつまいもなどを取り入れると、満足感を得ながら無理なく砂糖を減らせます。
乳製品・小麦など消化に負担をかけやすい食品
牛乳やチーズ、アイスクリームなどの乳製品は、人によっては乳糖不耐症の症状(下痢やお腹の張り)を引き起こすことがあります。
また、小麦を使ったパンやパスタ、ピザなどはグルテンが消化に時間を要し、腸内にガスをためやすいため、準備食では避けた方が安心です。
準備食の主食は、おかゆやうどん、玄米を柔らかく炊いたものを選びましょう。
アルコール・カフェイン
アルコールは肝臓に大きな負担を与え、さらに利尿作用によって脱水を招きやすくなります。ビールやワイン、日本酒だけでなく、アルコール入りチョコや梅酒なども控えるのが理想です。
また、カフェインを含むコーヒーやエナジードリンク、緑茶や紅茶も胃腸を刺激し、断食中の頭痛や不調につながることがあります。
準備食の期間は、麦茶やハーブティー、白湯などカフェインレスの飲み物に切り替えておくと安心です。
準備食で控えたいものについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:ファスティングの準備食で食べてはいけないものは?管理栄養士が解説
準備食のメニュー例
 準備食では、消化にやさしく栄養のバランスが取れる食事を心がけることが大切です。
準備食では、消化にやさしく栄養のバランスが取れる食事を心がけることが大切です。
ここでは、1〜2日間を想定した具体的な献立例をご紹介します。実際の生活に取り入れやすい内容なので、参考にしてみてください。
1日目の献立
準備食初日は、普段の食事から脂っこいものや砂糖を減らし、胃腸を少しずつ休ませるイメージです。
| 朝食 | 野菜スープ+おにぎり |
| 昼食 | おかゆ+漬物 |
| 夕食 | 味噌汁+蒸し野菜 |
シンプルながら、食物繊維・発酵食品・水分を取り入れられるメニューです。
2日目の献立(例:朝=フルーツ+豆乳ヨーグルト、昼=うどん+海藻、夜=雑炊+温野菜)
| 朝食 | 野菜スープ+おにぎり |
| 昼食 | おかゆ+漬物 |
| 夕食 | 味噌汁+蒸し野菜 |
軽めの食事でも必要な栄養素を補い、身体を快適に整えられます。
簡単アレンジ例(具沢山味噌汁、蒸し野菜プレートなど)
毎回同じ献立では飽きやすいため、少しの工夫でバリエーションを持たせるのもおすすめです。
| メニュー | おすすめアレンジ |
| 味噌汁 | 豆腐・きのこ・野菜をたっぷり入れて具沢山に |
| 蒸し野菜 | キャベツ・ブロッコリー・じゃがいもなどを蒸して、塩やごまを添えてプレートに盛り付けたら見た目も華やかに |
| 野菜スムージー | ほうれん草やバナナを豆乳でブレンドしてジュース感覚に |
準備食は制限ではなく身体を整える時間と考え、楽しみながら取り入れることが大切です。
準備食でおすすめのメニューについては、こちらの記事で紹介しています。
関連記事:ファスティングの準備食でおすすめメニュー!管理栄養士の厳選レシピ5選!
よくある質問(FAQ)

準備食に関するよくある質問にお答えします。
準備食は必ず必要?
準備食は絶対に必要というわけではありません。ただし、準備食をおこなうことで断食や検査がスムーズになり、体調不良を防げるためできれば実施すべきです。
とくに初めてファスティングに挑戦する方は、準備食を取り入れることで成功率がぐっと高まります。
コンビニで準備食はできますか?
コンビニで販売されている商品を使用して準備食をおこなうことは可能です。
おにぎり(梅や昆布などシンプルな具)、カット野菜やサラダチキン、具だくさん味噌汁、無糖ヨーグルトなどを組み合わせれば、コンビニでも手軽に準備食を整えられます。
コンビニ飯を使った準備食については、こちらの記事で詳しく解説しております。
関連記事:【コンビニで買える!】ファスティング成功のためのおすすめ回復食紹介!
準備食を省略して断食したらどうなる?
いきなり断食に入ると、頭痛や便秘、だるさなどの不調が起こりやすくなります。また、胃腸に負担が残ったままだと、せっかくの断食や検査の効果を十分に得られない可能性があります。
体調を安定させるためにも、少なくとも前日だけでも準備食を実施しましょう。
まとめ|準備食で身体を整えてファスティングを成功させよう
準備食は、ファスティングや健康診断、手術前などに身体を整えるための大切なステップです。
消化にやさしい食材を選び、胃腸を休ませておくことで、不調を防ぎながらスムーズに本番へ移行できます。
準備食のポイント
-
消化にやさしい食材を選ぶ(おかゆ、うどん、蒸し野菜など)
-
「まごわやさしい」を意識してバランスよく取り入れる
-
発酵食品や水分をプラスして腸内環境を整える
-
脂っこい料理や砂糖、アルコール・カフェインは控える
-
忙しい場合でも、最低1日前だけでも実践する
準備食は「面倒な制限」ではなく、「身体を整えるための準備期間」と考えることが大切です。忙しくても、前日だけでも実践することで十分に効果が期待できます。
近日中にファスティングや健康診断を控えている方は、ぜひ今回ご紹介した食材やメニューを取り入れ、準備食から身体を整えてみてください。